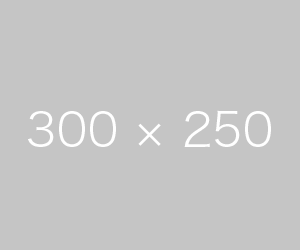こんにちは。新潟県よろず支援拠点コーディネーターの早川芙美子です!
食品の商品開発支援を担当しています。よろしくお願いいたします。
さて、今回は「食品開発の試作と検証」について書いてみたいと思います。「食」の商品化にこれから着手する方や、着手したばかりの方に、是非読んでいただきたい内容です。
食品の商品開発において、試作と検証は欠かせません。当たり前のことを言っているようですが、とても重要なことです。
例えば、既存のメニューや調味料などを他店に卸す場合。レシピは既にあるため、数回の試作で、それほど時間や手間をかけずに商品化できるのでは?と考えている方に、ときどき出会います。ですが、試作や検証が足りないことで、商品化しても思うような商品に仕上げられず、期待した売上に届かないことも、よくあります。
そこで、試作のステップと検証のポイントについて、まとめてみました。
【試作のステップ】
◎レシピ開発:原材料の選定、配合比率の検討。
レシピが既にあっても、数量に応じて、原材料の変更が必要な場合があります。
また、製造委託の場合、委託先の設備に応じて、配合比率の変更が必要な場合があります。ですので、レシピについては、想定している数量や設備に応じて、見直されることをおすすめします。製造工程についても同様です。
◎包装資材の選定:デザインや材質の検討。
立案したコンセプトを知らせるデザインについて、デザイナーさんに相談されることをおすすめします。自分でできる方は、ご自身でどうぞ!
材質は食品期限に関わる重要な要素です。何パターンか候補を選定後、試作品を包装し、保存試験をはじめましょう。
◎試作(方向性の確認):大まかな味や食感を確認。
コンセプトに合った製品に仕上がっているか確認します。合っていなければ、再試作に進みます。
◎試作(ブラッシュアップ):味の調整、コスト等の見直し。
試作を繰り返し、コンセプトに合う製品へ近づけていきます。また、製造委託の場合は、実際の製造ラインで作れるかテストが必要です。
【検証のポイント】
◎味・食感の評価:試食会、官能評価の実施。
試作後は、毎回試食をして、コンセプトに合っているのか確認します。評価表を作成し、評価する項目を決めておくのがおすすめです。
◎保存試験:食品期限や品質の安定性をチェック。
微生物検査や理化学検査だけでなく、官能検査も必要です。味・食感の他に、色や外観なども含めて経時変化を確認しましょう。
期限が切れる頃の状態をチェックし忘れている方、ときどきいらっしゃいます。食品期限の設定方法に不安がある方、いつでも相談してください!
◎試食会:ターゲットに試食してもらいフィードバックを得る。
この機会を得るのは難しいかもしれません。ですが、フィードバックを商品に反映させることでブラッシュアップが進みます。売上拡大のヒントが得られる大切な機会だと思います。
試作のステップも検証のポイントも、項目は多くはありませんが、内容は濃いものです。数回の試作で、というスケジュール感は薄れたのではないかと思います。
また、試作の前に済ませておく、商品企画や原価試算については、今回は触れていませんが、これも商品化において不可欠な工程です。
「食品開発の試作と検証」についてまとめました。
試作と検証は、商品開発の成功を左右する重要な工程です。試行錯誤を繰り返し、是非、ヒット商品に育て上げていただきたいと思います!
もっと知りたい、この部分がよくわからないなどありましたら、お気軽にご相談ください。
皆様のご相談をお待ちしております!
ご相談申込フォーム